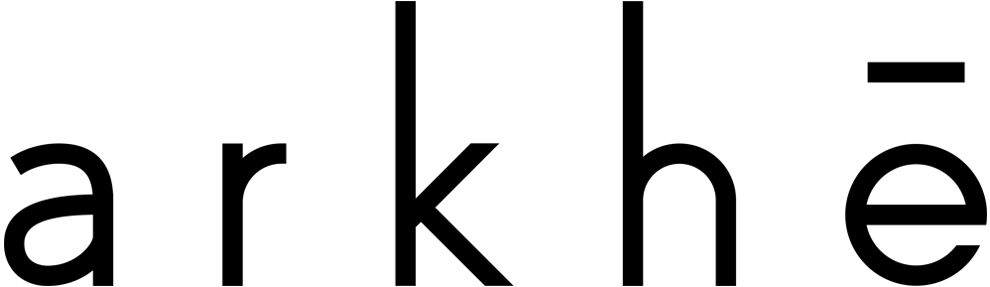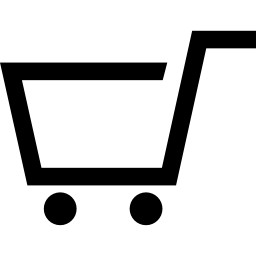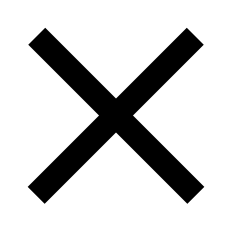Blog
Mail magazineメルマガ登録
arkheはファッション/アート/東京のグルメやショップの情報をお届けしています。
配信頻度:月に1〜4通
ビジネスの観点から紐解く「ファッションショー」が奇抜な理由

知っているようでよく知らないコレクションの世界
ファッション業界内外の人に関わらず、知っているようでよく知らないのが「コレクション」の世界ではないでしょうか。
ファッションの世界では、最新デザインの洋服がショー形式で発表される「コレクション」というファッションイベントが毎年開催されています。
とりわけ、「オートクチュール」と呼ばれる「デザイナー主導のオーダーメイド高級仕立服」のファッションショーは豪華絢爛(ある意味では「奇抜」)であり、世界でも2か所、パリ(パリ・オートクチュールコレクション)とローマ(ローマ・オートクチュールコレクション)だけで開催されています。
「プレタポルテ」と呼ばれる「高級既製服」のファッションショーは、年2回、パリ・ミラノ・ロンドン・ニューヨークで開かれており、「四大コレクション」と呼ばれています。それらに続く形で、東京でも、「東京コレクション」と通称されるファッションイベントが開催されています(現在の正式名称は「東京ファッションウィーク」)。
ファッションショーの運営はハイコスト

こうしたファッションショーに参加したことがない方でも、雑誌やインターネットのニュース記事で、こうしたショーの様子を写しだした華やかな写真を見る機会があるのではないかと思います。スタイリッシュな会場で、大勢のモデル達が、最新のデザインの衣服を身に纏ってランウェイを歩く姿は、実に華やかなものです。
こうした華やかなファッションショーの運営には、当然のことながら、大きな費用がかかります。
出展するアパレルブランド、それも、これから知名度を高めて売り出していきたいと考えている新進気鋭のブランドの運営者だけで、イベント全体の運営費を工面することは現実的に不可能です。
それでは実際のところ、どのようにして、こうしたファッションショーの運営は行われているのでしょうか?
ファッションショーの運営は、ファッション業界の川上から川下に至るまで、あらゆる関係会社が名を連ねる業界団体が担うのが一般的です。「東京ファッションウィーク」の場合は、「一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構」という業界団体が主催者として運営を行っています。
「一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構」の直近の決算報告書(2018年度分)を見てみると、「コレクション事業」、すなわちファッションショー関連で、年間6.15億円の支出が出ていることがわかります(事業費+管理費合計)。
それらの費用の詳細な内訳は出ていませんが、類似のショーの決算報告書を参考にすれば、関係各所、とりわけ、来場するマスコミやプレスの手配・調整を始め、ショーを運営するためのあらゆる関連業務を滞りなく進めるために必要な人件費や、会場の当日オペレーション・公式スチールや映像の記録等にかかわる外部委託費がその内訳であると推定され、それらに対して、これだけの費用がかかっているわけです。
こうした費用に対して、収入は年間6.08億円ということで、実質的に(わずかではあるものの)赤字のイベントとなっているわけです。しかも、収入の三分の二ほどにあたる3.8億円は、冠スポンサー(東京の場合、2011年10月開催分からはメルセデス・ベンツ日本、2016年10月開催分からはアマゾン・ジャパン合同会社、2019年10月開催分からは楽天株式会社)からの協賛金で賄っている構造になっています。
これだけの協賛金があっても、それでも、(若干ですが)赤字となっているということです。これは、最終的には、運営元の業界団体の負担となるわけです。
つまり、業界団体(および冠スポンサー)がここまでの負担を行うことで、ファッションショーは、経済的になんとか成り立っているのです(一時期、国が予算を割いて事業費の一部を賄っていた時代もありましたが、財政難もあり、現在では支援は打ち切られています)。
そのため、出展するアパレルブランドは、基本的には参加登録料と会場使用料を支払うだけで、ファッションショーに参加することができるわけです。
とはいえ、それなりの大きさの会場を確保するためには、それだけでも数百万円が必要になりますし、ただ単に参加する権利と会場を確保しさえすれば、ショーが行えるというわけでもありません。
何より、モデルを確保しなければなりません。メイクも必要です。人気のモデルともなれば、ギャランティは相当な額にのぼります。そして、ショーをショーとして成り立たせるためには、さまざまな演出を用意する必要があります。
もちろん、「ただ単にランウェイを歩くだけ」のシンプルなショーでも、ショーとして成り立ちはしますが、「話題を集める」ためには、それだけでは十分ではありません。「話題を集める」ためには、派手な音楽・照明といった要素だけではなく、作りこんだ舞台装置、さらには、サプライズのための様々な仕掛けの企画も必要です。これらを用意するためには、相当な費用が必要になります。
それだけではありません。ショーそのものだけではなく、その周辺を整えるのにも費用がかかるのです。
招待客を接待するために、ケータリングやノベルティの手配が必要です。当日の会場対応も、自社の関係者だけで回せないとなると、さまざまな関連費用がかかってきます。それらが積みあがると、数百万円では足らず、一回のショーを行うのに、場合によっては2,000万円以上かかってしまうことになるわけです。
東京ファッションウィークであってもこの規模の費用がかかるわけですから、世界で最も注目が集まるパリコレともなると、競争は激化し、演出にかかる費用はさらに増加していきます。とりわけオートクチュールのコレクションともなると、招待客も世界屈指のセレブリティばかりですから、そうした方々へのVIP対応だけでも莫大な費用がかかるものです。
このように、「ファッションショーを行う(コレクションに参加する)」ということには、莫大なお金がかかるものなのです。
ブランドが期待するリターンとは
このように、場合によっては数千万円にものぼるコストがかかる以上、ファッションショーに参加するブランドとしては、それに見合ったリターンを期待するのがビジネスとして当然のことです。
何の見返りもなく、お金だけ出ていくだけでは、ビジネスとして存続させていくことは難しくなります。
メディアへの露出

ブランドが期待するリターンの1つ目は、メディアへの露出です。
ショーには、ファッション専門雑誌、さらには一般媒体の記者も数多く参加します。写真記事だけでなく、当日収録された映像は、テレビ放送・インターネット動画配信メディアなどを通じて広く拡散されていきます。認知度を広げたいと考えている新興ブランドは、ここで注目を集めるために、メディアからの注目を集め、報道の中での自社の露出割合を増やすために、また、最終的に、世の中の注目を集めるために、鮮烈な(時に奇抜な)ショーを展開しようとするわけです。
昨今では、メディアを通じて情報発信をするだけでなく、ブランドの側が、直接、自社の運営するオウンドメディア・動画配信チャンネル・SNSアカウントを通じて、ダイレクトに世の中に対して情報発信することも可能になっているため、この傾向に拍車がかかっています。
ファッションの専門家・専門媒体記者や、洋服を商品として取り扱う卸・リテールのバイヤー向けに、「この洋服の、どこが、どのように魅力的なのか」を丁寧に語り掛けることよりも、「世の中において、いかに注目と話題を集めるか?」ということに力点が移ってきているのです。
そのため、海外著名ブランドのショーにおいては、ファッションショーの会場に観覧車やメリーゴーランド(!)を設置したり、キャットウォークを水で浸してその上を(まるで浜辺をモデルが歩いているかのように)歩かせるような演出を行うようなケースも出てきています。
写真や映像のサムネイルを見るだけで、「なんだこれは!」と注目してもらえるように、インパクト重視の、そのような演出を行うわけです。膨大な情報が溢れるスマートフォンのタイムラインの中で、自社ブランド・製品に注目してもらうためには、そのような仕掛けが必要である、というわけです。
ステータスを創り出す

加えて、ブランドが期待するリターンとしては、ショーに参加することで得られる「ステータス」の存在があります。
高額なショーを催すためには、財力が必要です。ショーに参加した、ということ自体が、そのブランドの運営元が有する財力の裏付けとなり、それが「ステータス(言い換えれば、社会的信用)」を生む、というわけです。
しかしながら、既に名をなし財をなしている著名ブランドであればともかく、新興のブランドの場合、「ショーに参加できている」ということが、すなわち「財力がある」ことの証明となるともいえません。
無理をして初期資本をコレクション参加のためにつぎ込んだものの、そのブランドの洋服を実際に購入してくれるような「本当の意味でのファン」をしっかりと築き上げることができず、結果的に経済的に破綻してしまい、事業を畳まざるを得なくなるようなブランドもあるわけです。
現代においては、そのような構造を分かっている人も増えてきていますから、ショーに参加するだけで簡単にステータスを創っていけるような時代ではなくなってきているとも言えます。ましてや、「お金を払えば参加できるんでしょ」と思われてしまうようなコレクションに参加するだけではステータスにつながらないことは自明でしょう。
ファッションビジネスを、「一攫千金のビジネス」と捉え、「世の中で一時的に大きな話題を集めて、一気に売りさばいて大きく儲けられるかどうかが勝負の商い」と捉えるならば、こうしたショーにお金を投資して勝負を賭けていくという選択も合理的でないとは言えません。
また、ファッションビジネスを、「デザイナーとしての一種の自己表現の手段」と捉え、最終的に採算が合おうが合うまいが構わない、と考えるならば、元が取れなくとも、多くの人に自社ブランドや製品、そしてそれらが体現する価値観を広く発信していくための格好の手段であるファッションショーを活用する、という選択も、合理的でないとは言えません。
しかしながら、ファッションの市場は、年々縮小しています。
アルケーは、これを、「現代の日本を生きる人々がファッションに求めるものが変化(進化)してきていることの現れであると考えています。
すなわち、「話題になっている流行の象徴としての衣服を身に纏いたい」というニーズでもなく、「デザイナーの自己表現に共振しつつ、自分自身のアイデンティティの表出としての衣服を身に纏いたい」というニーズでもなく、「日々の暮らしを生きる自分達が本当に心地よいと感じられる、上質な衣服を身に纏いたい」というニーズこそが、「現代日本においてファッションに求められているもの」であると考えています。
ファッションショーの歴史的役割は終わり、ソーシャルの時代が始まる

もちろん、第二次世界大戦の終焉とともに始まった<現代>という時代、つまり、世界的に、「ファッションとは何か」「我々はどのように生きるべきか」ということを模索していた時代においては、ファッションショーが果たした役割というものは非常に大きなものでした。
東京コレクションを創始(発起)した、川久保玲、松田光弘、三宅一生、森英恵、山本寛斎、山本耀司といった偉大なる先人達に敬意を表しつつも、経済的にも社会的にも成熟が進んできている現代の日本の社会においては、「ファッションショー」とは異なる回路で、衣服の作り手と、衣服を身に纏う人々(~日々を生きるすべての人々~)との間の関係性を紡ぎなおしていく必要があるのではないでしょうか。
ファッションショーへの参加をはじめとする、「とにかく大量のインプレッションを稼いで、できるだけ多くの人に数多く売りさばいていこう」というような「大量消費社会型」のマーケティングアプローチでは、現代を生きる人々の繊細な暮らしのニーズに応えていけないのでは、と考えます。
なにより、商品の宣伝にかかる巨額の費用を、価格に転嫁してしまうのでは、ビジネスのありかたとして本末転倒だろうと考えます。そうしたやりかたでは、本当にその衣服を求める人に、手にとって頂きやすい良心的な価格で製品を届けていくことが難しくなってしまう、と考えます。
このような流れは、アルケーだけの考えではなく、世の中全体のうねりのようなものなのかもしれません。
1987年に第1回が開催された「大阪コレクション」に至っては、2005年春夏コレクション(2004年開催)を最後に、早くも幕を閉じています。
東京コレクション(東京ファッションウィーク)ですら、来場者数は減少の傾向が見て取れます。
2013年春に開催された「メルセデス・ベンツ ファッション・ウィーク 東京」においては37ブランドのショーが行われ、主たるイベントの来場者数は3万7900人でしたが、2018年春に開催された「Amazon Fashion Week TOKYO」においては59ブランドのショーが行われましたが、主たるイベントの来場者数は2万3800人だったと言われています。5年間で、半分近い減少幅となっているわけです。
近年では、いわゆる「リアル・クローズ」の発表イベントであるファッションショーも多数生まれてきており、話題ともなっていますが、「人気モデルと会える有料お祭りイベント」としての側面が強く、世の中に欠かせないファッション業界の基礎インフラとして機能しているとは言い難いのではないでしょうか。
今、真に求められているものは、「人々が、本当に自分が求める衣服と出会える場(出会える情報チャネル)」ではないでしょうか。
洋服よりもモデル目当てで、ただ単にお祭りとして盛り上がるだけの<ショー>という形式だけでは、本当の意味での「衣服」の進化はありえないのではないかと考えます。
過剰な演出が施された非日常的な空間で、「モデル」が衣服を着ている様子を見ていても、現実離れした印象しか持てないという人が増えてきているのが現代だと思います。
多くの人にとって、ファッションは、日常そのもの、生活そのものであって、「その服が、暮らしをどのように快適に、過ごしやすいものにしてくれるのか」こそが重要であるわけです。
そうしたことを伝えていくためには、<共感>を生む、素敵な写真1枚、シンプルな映像1本で十分だったりするわけです。ああ、いいな、こんなふうにこういう服を着て、こんなふうに暮らしていきたいな、と思える写真が、じわーっと広がっていけば、それで十分なわけです。
そうして、衣服を作る人と、着る人が、ダイレクトにつながっていく。それは、幸せなつながりのカタチであり、健全なビジネスのありかたであると言えないでしょうか。
あまりお金をかけずに、あるがままの製品の良さを、その製品が普段使われるであろう日常的な空間で、そのままに映し出した写真や映像、それに添えられた丁寧な言葉が、ソーシャルメディアを通じて静かに広がっていく。
こうしたカタチこそが、これからの時代においてますます求められていくビジネスのありかたではないでしょうか。
顧客にとって本当に必要なものを見極める。そして、優れた品質のプロダクトをつくり、無駄をなくした流通の仕組みを通して、できる限り手に取っていただきやすい価格で販売を行っていく。
宣伝においても同様に、押し付けがましく騒ぎ立てて「宣伝」するのではなく、本質的な価値を丁寧に発信していく。そうして発信した丁寧なメッセージが、自然と広がっていく。
そんなカタチ。
arkhē(アルケー)は、そんなカタチを、じっくりと、丁寧に、作り上げていきたいと思っています。
関連記事
ビジカジと相性抜群なきれいめレザースニーカーの魅力に迫ります
ビジネスマンの足元に馴染みのある革靴はスーツスタイルを上品に演出し、着こなしを格上げする効果があります。 一方、近年はビジネスのカジュアル化に伴ってスーツにスニーカーを合わせることが一般的になり、社会にも受…
一本あって損なし。ブラックデニムを使った大人メンズの着こなし集
ラフになりすぎず、履くだけで一気に大人っぽく仕上がるブラックデニム。 カジュアルなインディゴブルーや清潔感のあるホワイトなど、デニムのカラーにはそれぞれの良さがありますが、スタイリングで「モノトーンでまとめ…
オーガニックコットンとは。肌触りは良いのか?おすすめブランド等紹介しています!
オーガニックコットンとは オーガニックコットンとは、化学合成肥料や農薬・除草剤を使用せずに自然の太陽光や水、大地の栄養で栽培・生産された綿花(コットン)のことです。 オーガニックコットンを名乗るためには厳密な認証機関の審…
ラフにかぶれてお洒落度が上がるバケットハット|メンズコーデ18選
バケツをひっくり返したような円筒型のクラウンを持ち、下に向かって傾斜していく短めのつばが特徴的なバケットハット。 出かける準備をして鏡で見ると何となく感じる物足りなさも解決してくれ、おしゃれ度をぐんと上げてくれます。 バ…